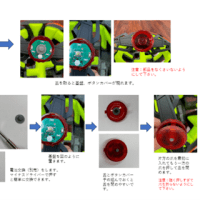中外時評 二・二六事件と謎のスクープ 80年前のメディアに思う
論説副委員長 大島三緒
2016/2/21 3:30 日経朝刊
その日から間もなく80年になる。1936年2月26日の朝、いわゆる皇道派の青年将校が約1500人の下士官と兵を率い、首相官邸などを襲った二・二六事件である。
昭和史の大きな転換点となったこの出来事は、メディアにも激震をもたらした。
内務省が記事差し止めを命じたため当日夕刊に事件のニュースは載らず、かたや青年将校らは東京朝日新聞社の襲撃に及ぶ。銃口を前にし、活字ケースを倒され、しかし主筆・緒方竹虎は毅然と対応したとされる。
とはいえ各紙とも事件の性格を測りかね、報道解禁となった27日朝刊以降も右往左往したようだ。表現も当初の「蹶起(けっき)」から「叛乱(はんらん)」へ。紙面は公式発表が中心だった。あとは「戒厳令下の帝都」の雑観記事ばかりが目立つ。
日本経済新聞の前身である中外商業新報も例外ではない。しかし、じつは水面下で、驚きのスクープをつかんだ記者がいたことはほとんど忘れられている。
その人、和田日出吉はもともと時事新報で活躍したジャーナリストだった。社会部長兼論説委員として「中外」に移ってきて間もない和田は、事件の朝、騒然とした編集局で一本の電話を受ける。
「もしもし、栗原です」と相手は名乗った。聞き覚えのある声……青年将校のひとり、栗原安秀中尉に違いない。「いま、どこにいる?」「首相官邸にいます」。かねて面識のある男が、占拠した先から連絡をよこしたのだ。まさかの展開である。
「そちらに乗り込ましてもらいたい」。栗原に告げるや和田は息せき切って社の車を飛ばした。そして銃剣をかいくぐり、官邸にたどり着き、栗原との面会に成功する。無残に荒らされた邸内を取材してまわり、将校らが、岡田啓介首相と思い込んで殺害した後に布団をかぶせた秘書官の遺体を目にしてもいる。
これが紙面で報じられていれば大スクープだったが、特ダネは日の目を見ることなく日々が過ぎた。やがて事件から5カ月後。「中央公論」8月号に突如、肩書なしで和田の手記が登場する。
「二・二六事件 首相官邸一番乗りの記」。こう題した一文は、いま読んでも迫力十分である。伏せ字がかなり多く、随所にぼかした言い回しもあるから発表にこぎつけるのに相当苦労したに違いない。しかし編集後記いわく「この記録は歴史的に残るものとして本号の圧巻である」。
まさに「歴史的」記事なのだが、これほどの特ダネも不十分なかたちでしか世に問えなかった当時のメディア状況を、あらためて心に留めておく必要があろう。くだんの和田と栗原の電話も当局は察知しており、憲兵隊が「中外」本社に踏み込んでいる。
麹町憲兵分隊曹長だった小坂慶助の回想記「特高」によれば、小坂らは守衛にピストルを突きつけて社内に乱入、和田を一時検束した。小坂はこの経緯を「人騒がせの一幕」と振り返っているが、記事公表が異例の形になった背景をうかがわせる話である。
さて、あらためて事件当時の「中外」紙面を眺めれば、それでも1936年はまだ世の中は平穏だった。「家庭と婦人」欄は春の最新モードを紹介し、社会面では大雪に見舞われた街の様子をユーモラスに描いている。
和田の記事を載せた「中央公論」8月号も寄稿者は多彩だ。三木清や長谷川如是閑、芦田均……。名だたるリベラリストが筆をふるっていた。こういう人たちがものを言えなくなるのは、あっという間のことであった。
事件の翌年には日中戦争が始まり、社会から急速に自由が失われていく。青年将校らの意図がどうであれ、結果として「二・二六」は軍部の暴走を後押しして破滅への道を開いていったのだ。
そういう端境期に謎の多いスクープを放った和田だが、わずか2年ほどで「中外」を辞して満州(現・中国東北部)へ渡る。そして女優の木暮実千代と結婚して引き揚げ、戦後はもっぱら売れっ子の旦那として生きた。
「彼は『中外』で自ら小説も書いていたんです。ちょっと早めに出社して夕刊の連載を書いたんだぞって、懐かしがっていましたね」。木暮のおいに当たる作家の黒川鍾信さん(77)は、和田からよくそんな話を聞いた。
その作品は「二・二六」の約2カ月後から150回ほど掲載された人情もの「燕子花(かきつばた)」である。この異能の人は、そうやって息苦しい時代をしのごうとしていたのかもしれない。
論説副委員長 大島三緒
2016/2/21 3:30 日経朝刊
その日から間もなく80年になる。1936年2月26日の朝、いわゆる皇道派の青年将校が約1500人の下士官と兵を率い、首相官邸などを襲った二・二六事件である。
昭和史の大きな転換点となったこの出来事は、メディアにも激震をもたらした。
内務省が記事差し止めを命じたため当日夕刊に事件のニュースは載らず、かたや青年将校らは東京朝日新聞社の襲撃に及ぶ。銃口を前にし、活字ケースを倒され、しかし主筆・緒方竹虎は毅然と対応したとされる。
とはいえ各紙とも事件の性格を測りかね、報道解禁となった27日朝刊以降も右往左往したようだ。表現も当初の「蹶起(けっき)」から「叛乱(はんらん)」へ。紙面は公式発表が中心だった。あとは「戒厳令下の帝都」の雑観記事ばかりが目立つ。
日本経済新聞の前身である中外商業新報も例外ではない。しかし、じつは水面下で、驚きのスクープをつかんだ記者がいたことはほとんど忘れられている。
その人、和田日出吉はもともと時事新報で活躍したジャーナリストだった。社会部長兼論説委員として「中外」に移ってきて間もない和田は、事件の朝、騒然とした編集局で一本の電話を受ける。
「もしもし、栗原です」と相手は名乗った。聞き覚えのある声……青年将校のひとり、栗原安秀中尉に違いない。「いま、どこにいる?」「首相官邸にいます」。かねて面識のある男が、占拠した先から連絡をよこしたのだ。まさかの展開である。
「そちらに乗り込ましてもらいたい」。栗原に告げるや和田は息せき切って社の車を飛ばした。そして銃剣をかいくぐり、官邸にたどり着き、栗原との面会に成功する。無残に荒らされた邸内を取材してまわり、将校らが、岡田啓介首相と思い込んで殺害した後に布団をかぶせた秘書官の遺体を目にしてもいる。
これが紙面で報じられていれば大スクープだったが、特ダネは日の目を見ることなく日々が過ぎた。やがて事件から5カ月後。「中央公論」8月号に突如、肩書なしで和田の手記が登場する。
「二・二六事件 首相官邸一番乗りの記」。こう題した一文は、いま読んでも迫力十分である。伏せ字がかなり多く、随所にぼかした言い回しもあるから発表にこぎつけるのに相当苦労したに違いない。しかし編集後記いわく「この記録は歴史的に残るものとして本号の圧巻である」。
まさに「歴史的」記事なのだが、これほどの特ダネも不十分なかたちでしか世に問えなかった当時のメディア状況を、あらためて心に留めておく必要があろう。くだんの和田と栗原の電話も当局は察知しており、憲兵隊が「中外」本社に踏み込んでいる。
麹町憲兵分隊曹長だった小坂慶助の回想記「特高」によれば、小坂らは守衛にピストルを突きつけて社内に乱入、和田を一時検束した。小坂はこの経緯を「人騒がせの一幕」と振り返っているが、記事公表が異例の形になった背景をうかがわせる話である。
さて、あらためて事件当時の「中外」紙面を眺めれば、それでも1936年はまだ世の中は平穏だった。「家庭と婦人」欄は春の最新モードを紹介し、社会面では大雪に見舞われた街の様子をユーモラスに描いている。
和田の記事を載せた「中央公論」8月号も寄稿者は多彩だ。三木清や長谷川如是閑、芦田均……。名だたるリベラリストが筆をふるっていた。こういう人たちがものを言えなくなるのは、あっという間のことであった。
事件の翌年には日中戦争が始まり、社会から急速に自由が失われていく。青年将校らの意図がどうであれ、結果として「二・二六」は軍部の暴走を後押しして破滅への道を開いていったのだ。
そういう端境期に謎の多いスクープを放った和田だが、わずか2年ほどで「中外」を辞して満州(現・中国東北部)へ渡る。そして女優の木暮実千代と結婚して引き揚げ、戦後はもっぱら売れっ子の旦那として生きた。
「彼は『中外』で自ら小説も書いていたんです。ちょっと早めに出社して夕刊の連載を書いたんだぞって、懐かしがっていましたね」。木暮のおいに当たる作家の黒川鍾信さん(77)は、和田からよくそんな話を聞いた。
その作品は「二・二六」の約2カ月後から150回ほど掲載された人情もの「燕子花(かきつばた)」である。この異能の人は、そうやって息苦しい時代をしのごうとしていたのかもしれない。