ものこと双発学会と協議会を発足させて、もうじき2年が経過します。この間に「学会員、協議会参加企業の積極的な参加のもと、毎月の研究会で“もの”から“もの・こと”への転換について議論がなされています。学会員の研究論文の発表と協議会の議論の報告会を2月27日に東京理科大学の神楽坂キャンパスで開催します。皆様もぜひご参加ください(2015年度 年次研究発表大会の詳細はこちら)。
さて、製造業のグローバル化によって、「ものづくり」だけに拘った競争で、日本企業が勝ち抜くのには限界が見え始めています。「ものづくり」と「ことづくり」の両方が高いレベルで揃うことが、持続的な競争力を身につけるカギとなっています。技術や製品を生み出すのが「ものづくり」、技術や製品、サービスを使って、これまでにない生活や社会のスタイルを生み出すのが「ことづくり」です。
こうした「ことづくり」の見本となる企業の1つが、米IBMです。今回は、日本アイ・ビー・エムの執行役員 研究開発担当である久世和資さんに、IBMが考える「もの・ことづくり」を伺います。久世さんには、「ものこと双発学会」の理事として議論に参加いただいています。
田中:「もの・ことづくり」において、IBMは、いち早く単なる「もの売り」から脱して、システムとして展開していた先駆け的な企業です。
そして今、先進国全体でものを売ることだけに頼った事業は縮小し、「ことづくり」、いわばIBMが先んじてきた、システムとして展開する企業が増えてきています。そこで、先行していたIBMが今、どのような方向を見据えているのか、伺いたいと考えています。IBMは、サービスを中心に据える中でも、その内容を常に転換しようとしているように見えます。

久世:これまでの経緯については、OBの田中さんの方が私より詳しいと思いますが、振り返ってみたいと思います。IBMは過去には、ハードウエアの売上が全体の半分以上を占めており1992年は52%でした。その後、ハードウエアの売上比率は下がり、2000年には24%、2010年には8%にまで下がりました。
とはいっても、IBMはハードウエアの事業を完全にやめたわけではありません。企業の基幹業務を担うメインフレーム・コンピューターやストレージなどの事業は続けていますし、半導体への研究開発も積極的に継続しています。
ハードウエアの売上比率が下がってきたのは、IT(情報技術)の分野を中心に、ハードウエアという「もの」だけでは事業が成り立たなくなってきているためです。一方、サービスのような「こと」だけでも難しく、その両方を効果的に組み合わせていかないと、お客様や企業の高度な課題を解決できなくなっています。このような環境の大きな変化の中、IBMは多くの変革に取り組んできています。
そのIBMで、私は日本における研究開発を担当しています。IBMの研究開発は、各国や各地域の特性を最大限に活用することが求められています。戦略、予算、計画などは、グローバルで統括されており、世界中の研究所と連携しながら研究開発を推進しています。IBMの研究所には、コーポレートに直結した基礎研究所と、製品を中心とする事業部に所属する開発研究所の2種類があります。我々、日本の開発研究である東京ラボには、その両方があります。
10年以上続いた事業部体制を改革
ここにきて、IBMは更に大きく変革しようとしています。その象徴的な出来事は、10年以上続けてきた事業の体制を2015年1月に大きく変えたことです。「もの・ことづくり」に関係する話なので、紹介したいと思います。
これまでは、ハードウエア製品事業、ソフトウエア製品事業、インフラストラクチャー関連サービス事業、アプリケーション(業務ごとの応用システム)関連サービス事業という、4つで構成されていました。
昨年1月の事業変革で、二つのサービスの事業以外は、大きく変わりました。まず、ハードウエアとソフトウエアのそれぞれの事業を廃して、両者を組み合わせたシステムズ事業とクラウド事業の二つを新設しました。さらに、従来の製品の切り口ではないソリューション(課題解決)の単位で複数の事業を新設しました。ワトソン事業、ヘルスケア事業、IoT事業、アナリティクス事業などです。「ワトソン」は、データを深く分析して、自ら学習するシステムで、これらを事業に適用したコグニティブ・ビジネスを称しています。これらソリューションの区分は、「ことづくり」の対象分野と捉えることもできます。
ハードウエアからソフトウエア、IT、クラウドコンピューティングを応用したサービスへと広がってきている中で、機器やハードウエアだけを提供する「ものづくり」のみでは、事業が成り立たなくなり、「ことづくり」の部分にも積極的に乗り出してきたことを象徴する事業形態の変遷だといえます。

田中:IBMは元々、システム寄りの事業に取り組んできました。お客さんのシステムを一括で請け負うような。いつの間にか、一部は単なる「もの売り」に近づいた場合もありながら、元々のシステム寄りの事業に戻してきた、という変化なのでしょうか。
久世:そう捉えることができるかもしれません。IBMは、1960年代に手掛けていた大型コンピューター「System/360」の時代から、システム寄りの売り方をしてきました。ITの第1の波である1960年代には、バックオフィス(管理業務)向けに、System/360を活用した在庫管理、顧客管理、生産管理などのシステムを提供してきました。この時代は、結果的に「ことづくり」を意識した「ものづくり」になっていたと言えます。
ITの第2の波は、パソコン(PC)の普及です。クライアント・サーバー(特定の役割を集中的に担当するサーバーと、利用者の操作する端末に役割を分けたコンピューティング手法)の時代に入ります。そこでは、ハードウエア単体に近かった従来のシステム構成に比べて、設計や構造が複雑になるので、ソフトウエアなどのミドルウエアにも注力していくことになります。
次の第3の波は、インターネットの登場です。IBMは「e-ビジネス」と呼んでいました。ビジネスや業務のさまざまな場面に、インターネットの活用を広げるものです。これまでのサーバーや業務ごとに構築されたシステムや応用アプリケーションを、インターネット上で提供することや、それらを統合的に開発・提供するシステム・インテグレーションが益々、重要になった時代です。また、ハードウエアから、ソフトウエア、アプリケーションまで管理も含めてアウトソーシングが登場しました。
第4の波は、ビッグデータ、モバイル、ソーシャル、クラウドなど、複数の新しい動きが同時に起こっているITの新潮流です。これは、ビジネスや事業へのITの利用方法を、これまでの方法から大きく変えることにもつながります。この新しい波を、いかに効果的に利用し、活用し、スピードと柔軟性を持って対応するかが非常に重要になってきます。
課題解決型の新しいコンピューター
そのための大きな戦略の1つとしてIBMが位置づけているのは、「コグニティブ・ビジネス」です。ワトソンは、その実現のための技術とソリューションの中核となっています。よく人工知能(AI)と比べられますが、異なるものです。
これまでは、人が、コンピューターにさせたい仕事を定義し、設計し、プログラムを開発し、処理に必要なデータを用意し、実行してきました。ところが、現在は、ビッグデータと呼ばれるように、データの量は爆発的に増え、データの種類も増えています。また、データの生成と処理速度は高速化しています。さらに、モバイルやソーシャルも含めITを使いたい場面や業務、アプリケーションは飛躍的に増えています。もはや、人がプログラムを作成し、必要なデータを集めて、実行するようなやり方では追いつきません。
そこで、IBMは、課題解決型の新しいコンピューターの実現を目指しています。人がプログラムを作成し、コンピューターに処理させるのではなく、解決したい課題を与えると、コンピューター自らが、必要なデータを集め、計算のロジックも最適化するコンピューターです。こうした構想を、IBMは「コグニティブ・コンピューティング」と呼んでいます。
コグニティブ・コンピューティングの先駆けとして、 2011年にすべてのジャンルに対する質問応答システムとしてワトソンが登場しました。米国で50年間以上続いている人気クイズ番組「ジョパディ」で、二人の歴代チャンピオンと対戦し、勝利することができました。その後、医療、金融、保険など、各分野でワトソンの実利用の共同開発を進めました。そして、2014年1月に、コグニティブ・コンピューティングをブランド化したワトソン事業部を設立しました。
もう一つの大きな戦略の転換は、データやコンテンツの保有です。IBMは、従来、アプリケーションやデータそのものは所有しませんでした。しかし、ITにおける第4の波を最大限にリードするためには、IBM自身がデータや知見、コンテンツ、知識を持つことだと考えています。
新しいITの時代では、ビッグデータである大量のデータから知識を構築することが重要になってきます。特定の分野のビッグデータとプロセスやノウハウなどの知識を持たない限り、その分野に関連する新しいIT事業も立ち行きにくいと予想しています。
そこで、ワトソン・ヘルス事業部は、米国で医療データを基に事業を展開している3つの企業、ファイテル、エクスプローリ、マージを買収しました。医療の分野は、データの取り扱いや規制が厳しい面があります。IBM自身が医療のコンテンツを持たない限り、事業を大きく広げられないリスクがあり、そうした制約を乗り越えるための転機となるはずです。
コグニティブ・コンピューティングという新たなコンピューターの仕組みをビジネスに活用することと、データと知識を自ら保有するということは、これまで経験したことのない時代に入ってきていることの象徴かもしれません。いずれも、「もの・ことづくり」に関連しています。
田中:IBMがコグニティブ・コンピューティングを主張し始めたのは、2000年前後でした。当時は、疑念を呈されることも多かった構想ですが、ようやく陽の目を見る時代に入ったと言えます。
コグニティブを事業にするには、応用を支えるデータが要ります。それを得る手法として、IBM自身で取り組むのではなく、知見を持つ企業と組むという、新たな仕組みで臨むのですね。IBMがうまいのは、このように新たな概念を具現化できるように整えてから、それを唱えていくところです。こうすることで、顧客の多くがついてきます。
年ごとの重要技術はグローバルで集約
久世:IBMは、具体的な「もの」を用意しながら、大きな構想やビジョンを具現化していくことを、ずっと繰り返してきています。
最近の新しい試みや活動の多くは、IBMが2000年から作成している「GTO(グローバル・テクノロジー・アウトルック)」で議論されたものが少なくありません。GTOは、各年ごとに、事業、市場、ビジネスに非常に大きな影響を与えうるテクノロジーの変化点をまとめたレポートです。研究所が中心になって作成しますが、その過程においては、関連事業部はもとより、社外の有識者やお客様の視点や意見、予測を取り入れます。GTOのオーナーは、CEO(最高経営責任者)となっています。開始当時は、ルー・ガースナー、その後、サミュエル・パルミザーノ、今は、ジニー・ロメッティがオーナーになっています。一年間かけて作成しますが、数名の専属スタッフに加えて、世界の研究所の数百名が作成に携わります。
毎年、年初に世界各地の12カ所の基礎研究所から、候補となるテーマが100件近く集まってきます。それらのテーマについて社内外と議論を重ね、グルーピングや取捨選択を繰り返し、 最終的にGTOに盛り込む技術トレンドは、4~7件に絞りこまれます。研究所だけでなく、事業部やお客様、大学など、さまざまな役割りや立場の部門や人の意見やアイデアを取り入れながら、議論を深めていきます。
GTOが完成すると、そのすべての内容を、まずCEOが半日かけて理解します。IBMのトップが自ら勉強するので、各事業部のトップも、真剣に理解し事業部の戦略に取り込みます。このように、GTOは研究所が中心に作成しますが、その結果は、IBM全体の経営戦略に活用されています。コグニティブ・コンピューティングのビジョンも、こうした中から出てきました。
コグニティブ・コンピューティングは、1990年代末に技術トレンドとしてGTOで示されました。GTOとは独立に、IBMの基礎研究所では、研究プロジェクトに対して、戦略、プラン、評価を行っています。その中に、「グランド・チャレンジ」と呼ばれるプログラムがあります。これは、長期的で実現がかなり難しいプロジェクト推進の仕組みで、常に10件程度、手がけています。
クイズ番組でチャンピオンに挑戦するコンピューター・ワトソンは、2006年頃に「グランド・チャレンジ」に位置付けられました。最初は2人の研究員の発想がきっかけです。2011年にクイズ番組で成果を上げるまで、4年間以上、約30名のコア研究チームのほか、数百名の研究者や技術者が開発チームとして関わっています。コア研究チームや開発チームには、もちろん、日本の基礎研究所からも参画しました。実は、日本は、基礎研究所も開発研究所も、ワトソンの重要な機能である自然言語の分析や理解では、30年前より世界でトップの専門技術集団です。
クイズ番組のジョバディは、50年以上も続いていますが、二度と同じ問題は出題されません。このため単純に過去問を記憶していても、新しい出題に対する答えは導くことはできません。
まず、自然言語で表現された問題を解析し、問われていることは何かをまず理解します。たとえば、人名なのか、地名なのか、年代なのかなどです。聞かれている内容がわかったら、次にワトソンが自分が持っているビッグデータの中から、解答の候補をできるだけ多く挙げ、それをすべて検証していきます。これを1~2秒の間に処理します。
ワトソンが拓く新市場
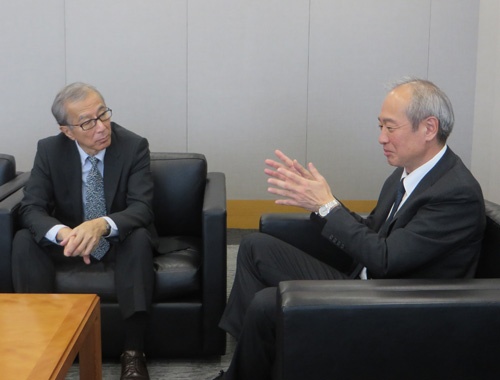
2011年に二人の歴代チャンピオンに対して、ワトソンは勝利することができました。ただ、ワトソンは、ジョパディで勝つことが、最終目標ではありませんでした。ワトソンのグランド・チャレンジがきっかけとなり、医療や保険など、さまざまな企業や研究機関から、ワトソンをビジネスや事業に使いたいという問い合わせがありました。ワトソンを実ビジネスに応用することにより、事業を変革したり、新しい市場を創ることが、より大きな我々の目標でした。
例えば、医療におけるワトソンの応用がその1つです。医療の世界では、新しい症例に加えて、治療法や薬なども、日々、進化しています。医療文献数も、5年間で二倍のペースで増えています。かたや、米国の場合、現場の医師が新しいことを勉強する時間は、平均して月に5時間しかありません。いくらベテランで優秀な医師でも、最新の知識がないと、最善の診断や治療をすることが難しくなります。このような状況ですので、新しい知識を学習し続けるワトソンが、医師の診断や治療のサポートをするという新しい医療の形態が重要になってくるはずです。
メモリアル・スローン・ケタリング癌センターでは、160万の癌の症例や関連の医療文献をワトソンに学習させ、医師の診断支援に活用しています。
また、創薬では、ベイラー医科大学と共同で、p53という癌細胞の抑制に効果がある新しい酵素などを発見するのに、ワトソンを利用しています。この分野は非常に有望で研究者も多く、世界中で、10万件近い論文が発表されており、今も増え続けています。研究者は、これらの論文を読むことが必要ですが、選択的、部分的にしか読むことはできません。一人で読むとすると10年以上かかってしまいます。これに対して、ワトソンは、数日ですべての論文を読み込み、学習できます。これまでに、p53に効果がある酵素は、1年に1つ見つかるかどうかでした。ベイラー医科大学では、ワトソンを利用することにより、数週間で6つも発見することができました。画期的な創薬のスピードの向上になりました。
遺伝子の世界でも、ニューヨークのゲノムセンター他でワトソンは活用されています。日本でも、東京大学とワトソン遺伝子分析システムによる共同研究が進められています。
(次回に続きます)
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。










