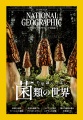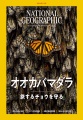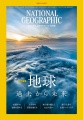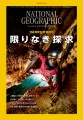冥王星はきわめて小さな天体だが、流れる氷河、興味深いくぼみのある領域、かすんだ空、多くの色を持つ風景など、信じられないほど多様な特徴が見られる。溶岩ではなく氷を噴き出す「氷の火山」や氷に浮かぶ山々があり、さらに衛星は予想もつかない動きをしているようだ。(参考記事:「冥王星“接近通過”をめぐる10の疑問に答える」)
2015年7月に冥王星へのフライバイを成功させたNASAの探査機「ニューホライズンズ」の科学者チームは、11月9日、米国天文学会惑星科学部会の年次総会で新たな観測結果を発表した。観測データが示す冥王星は、事前の予想とは全く異なる天体だった。(参考記事:「冥王星の三つの事前想像図」)
ニューホライズンズの主任研究者であるアラン・スターン氏は、「探査の成績は『優』ですが、予想の成績は『不可』です」と自己評価する。「冥王星系には驚かされてばかりです」。(参考記事:「ここまで鮮明に! 冥王星の写真の変遷を見てみよう」)
氷の火山
冥王星の南極付近にある2つのくぼみは氷の火山のカルデラかもしれない。2つのくぼみは、それぞれライト山とピカール山という巨大な山の上にある。どちらの山も、高さは数kmで、裾野の直径は100km以上ある。これはハワイの楯状火山に似た形と大きさだが、冥王星の火山から噴出するのは灼熱の溶岩ではなく氷のようだ。おそらく、氷の下の海から上がってくる、窒素、一酸化炭素、あるいは水の氷が混ざった、どろどろしたものだろう。(参考記事:「土星衛星タイタンに氷の火山?」)
NASAのエイムズ研究センターのジェフ・ムーア氏は、学会発表の際に、現時点ではこれらが本当に火山であると結論づけることはできないが、「その可能性は非常に高い」と語った。
もしそうなら、これらは太陽系外縁部で初めて発見された火山になる。研究チームは、さらなるデータによりこの発見を裏づけることを計画しているが、一部のメンバーはすでに強い確信を持っている。
同じくエイムズ研究センターのオリバー・ホワイト氏は、「頂上に穴がある大きな山を見たら、ふつう考えられることはただ1つです」と言う。「私には火山にしか見えません」
氷に浮かぶ山
冥王星の山々は、地球のような山より海に浮かぶ氷山に似ているようだ。ムーア氏によると、冥王星の山々の正体は水が凍った氷の塊で、おそらく窒素が凍った氷の「海」に浮いているという。一部の領域では、こうした山はロッキー山脈ほどの大きさになっているが、窒素や一酸化炭素の氷の海に比べて密度が低いため、海面から顔を出して浮かんでいられる。ムーア氏は発表で、「冥王星で最も大きい山々でさえ海に浮かんでいるのかもしれません」と述べた。
スプートニク平原と呼ばれる氷原の西の端近くでは、巨大なシート状の水の氷がひび割れて配置が変わり、ムーア氏いわく「無秩序な領域」ができている。形成されてから日が浅いなめらかな平原の近くに、幅40km、高さ5kmもある角ばったブロックが乱雑に連なり、無秩序に広がる山々を作っているのだ。新たな分析によると、スプートニク平原は形成されてから1000万年しか経っていないらしい。スターン氏は、「昨日生まれたばかりと言ってもよいくらいです」と言う。「小さな天体が、形成から数十億年後になっても大きなスケールで活動していることが分かったのは大発見です」
巨大な裂け目、内部の海
冥王星の表面には、スプートニク平原のように、信じられないほどなめらかな領域があるが、他の場所は、穴だらけだったり蛇革のようなうろこ状になっていたりする。スプートニク平原の西には、バージル・フォッサ(Virgill Fossa)などの巨大な裂け目がいくつもある。こうしたひび割れは、冥王星が膨らんで外殻が破裂したような見た目で、実際、そのようなことが起きた可能性がある。米ワシントン大学セントルイス校のビル・マッキノン氏は、「外殻の下でゆっくり冷えて凍ってゆく海が膨張したのかもしれません」と言う。科学者たちが推測しているように冥王星の外殻の下に液体の海が隠れているなら、この海がゆっくり凍って膨張すれば、外殻が破裂したような巨大な裂け目ができる可能性がある。
少なくて冷たい大気
ニューホライズンズによるフライバイの前まで、科学者たちは、冥王星には窒素を主成分とする大気が大量にあり、その量は冥王星の体積の7~8倍もあるかもしれないと予想していた。しかし、その大気はどんどん失われているとも考えられていて、冥王星が誕生してからの46億年間に表面から厚さ1km分の氷が昇華して失われたと推測する科学者もいた。
ニューホライズンズの科学者たちは、こうした予想はほぼ完全に間違っていたと言う。冥王星の大気は予想ほど多くなかったし、大気が失われるペースも予想ほど速くなかった。米サウスウェスト研究所のレスリー・ヤング氏は、「今回明らかになったペースなら、これまでに失われた氷は15cmほどでしょう」と言う。冥王星の窒素の大半は、冥王星の近くにとどまっている。奇妙な観測結果だが、これは、冥王星の大気中の高いところにシアン化水素があることにより説明できるかもしれない。そんなに大量のシアン化水素が見つかるとは誰も予想していなかったが、シアン化水素が大気の温度を大幅に下げて、冥王星のまわりにとどめるのに役立っている可能性がある。
予測不能の動きをする衛星
冥王星の4つの小さな衛星ステュクス、ニクス、ケルベロス、ヒドラの姿がついに明らかになった。冥王星系に関するほとんどの事実がそうであったように、これらの衛星も科学者の予想を超えて奇妙な天体だった。現在、欧州宇宙機関(ESA)のロゼッタ探査機が周回して探査しているアヒル型のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星と同様、ケルベロスとヒドラも2つのさらに小さい天体がゆっくり衝突して融合したように見える。米SETI研究所のマーク・ショーウォルター氏は、「過去には、冥王星の小さな衛星は4つ以上、少なくとも6つはあったのです」と言う。(参考記事:「冥王星の「踊る」衛星を発見」、「チュリュモフ彗星がアヒルの形になった理由」)
さらに奇妙なのは小さな衛星の自転の速さだ。一番速いのは10時間に1回のペースで自転しているヒドラだが、すべての衛星が予想より速く自転していた。「こんな衛星系は見たことがありません」とショーウォルター氏は言う。その上、ニクスのある面には赤みがかかった奇妙なクレーターがあり、科学者たちはそれをしっかり説明することができずにいる。また、小さい衛星の中で1つだけ黒い色をしていると予想されていたケルベロスは、実際にはほかの3つの衛星と同じ程度の明るさだった。